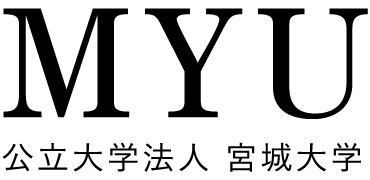![宮城大学を [知る] [学ぶ] [感じる]](/packages/ooc2020_theme/themes/myu_ooc2020/images/title_sub.png)
学生生活でよくあるご質問にお答えします(FAQ)
教育課程に関すること
Q:履修科目にはどのようなものがありますか
1年次には大学での学びに必要な基礎的なスキルを身に付けるための「基盤教育科目」、2年次以降には専門基礎を学ぶ科目、2年次後期からはより専門性の高い講義と演習・実習があります。各講義の概要はシラバスをご確認ください。
Q:履修科目を決めるにあたり、参考になるモデルのようなものはありますか
本学ウェブサイトに掲載されている履修ガイドに「履修モデル」が掲載されていますので、こちらを参考にしてください。
Q:取得できる科目数に上限はありますか
年次ごとに上限が定められています。本学ウェブサイトに掲載されている履修ガイドを参考にしてください。
Q:学類はどのように決定されますか
届出により1年次の3月末に学類が決まります。ただし希望者多数の学類は、1年次の成績やレポート、面接等による選考を経て学類が決まります。
実習に関すること(看護・食産希望者向け)
Q:実習時期はいつ頃ですか
- 看護学群:現カリキュラムでは、1年生後期から実習科目が始まります。
- 食産業学群:現カリキュラムでは、1年生前期から実習科目が始まります。
Q:実習内容はどのようなものですか
-
看護学群:看護学の基礎技術を学ぶ実習、領域別毎の実習(母性・小児・成人・老年・精神・在宅・地域)を踏まえ、最終的には各自が関心を持つ領域での実習を行います。
-
食産業学群:食機器や試薬の取り扱い等の基礎を学ぶ実験や、農場における作物実習、食品加工実習等が必修になり、他は学類や希望する研究室や興味のある科目によって変わってきます。
資格に関すること
Q:どのような資格を取得できますか
Q:在学中に資格を取ることはできますか
Q:資格を取得するにあたり履修が必要な科目はありますか
通学などに関すること
Q:学生の主な通学方法は何でしょうか
学生は、主に公共交通機関(バス)、自転車又は自動車により通学しています。詳細は本学ウェブサイト「通学方法」でご紹介していますので、ご確認ください。
Q:通学用定期券は購入できるでしょうか
本学が発行する通学証明書を各公共交通機関の窓口に持っていくことにより、通学用定期券を購入できます。
Q:県外から通学することは可能でしょうか
交通機関を乗り継ぐことで可能ではありますが、移動時間が長く午前中の講義への参加が難しくなります。これまでの県外合格者も、県内に引っ越して通学する学生がほとんどです。
一人暮らし・アパートに関すること
Q:学生寮はあるのでしょうか
学生寮はありません。
Q:大学でアパートの紹介をしてもらえるのでしょうか
大学生協にてアパートの紹介をしておりますので、そちらをご確認ください。
学校行事に関すること
Q:学校行事にはどのようなものがありますか
例年の大学行事としては、10月に大学祭が行われています。
奨学金に関すること
Q:どのような種類の奨学金がありますか
主な奨学金として、日本学生支援機構奨学金がありますが、こちらは、給付奨学金(返還不要)、貸与第一種奨学金(要返還・返還時無利子)、貸与第二種奨学金(要返還・返還時有利子)があります。また、被災時等に一時金が給付される制度もあります。
Q:日本学生支援機構以外の奨学金もありますか
財団や、地方自治体等の奨学金で、大学宛に募集案内の連絡が来たものについては、大学から皆さまへ周知をしています。(年間30件程度)
授業料・入学金・諸経費・雑費に関すること
Q:授業料の金額はいくらですか。また納付時期はいつですか。
授業料は年間535,800円を、前期と後期2回に分けて、267,900円ずつ納付いただきます。納付期日は現在、前期は5月31日、後期は10月31日です。
詳細はこちらをご確認ください。
Q:授業料の減免等の制度はありますか
修学支援新制度の他、本学独自の授業料減免制度があります。ただし、本学独自の授業料減免制度は、留学生等の一部の学生を除き経過措置による対応となっていますので、原則新入生は申請できません。
Q:教科書代はいくらですか
教科書は受講する講義によって変わるため、一概には回答できません。シラバスに使用する教科書・参考書に関する記載がありますので、そちらをもとにご確認ください。なお、教科書は大学生協にて販売します。
Q:ユニフォーム代はいくらですか
- 看護学群:購入する内容・年度毎に異なりますが、以下参考にしてください。(下記値段は令和2年度のもの)
半袖上着2セット:12,100円~16,980円、パンタロン※女性(2セット):約9,800円、スラックス※男性(2セット):10,800円、カーディガン1セット:3,900円、聴診器:8,900円~12,900円 - 食産業学群:購入する内容によって異なりますが、以下参考にしてください。
農場系実習用(つなぎ・長靴等)7,000円~10,000円、食材加工実習用(上下作業着・帽子等)7,000円、実験用(白衣+保護メガネ等)3,400円"
修学支援新制度に関すること
Q:修学支援新制度とは何ですか
「大学等の修学の支援に関する法律」により、経済的に厳しい状況にある学生に対し国が修学の支援を行う制度です。具体的な内容としては、日本学生支援機構による給付型奨学金及び大学による授業料の減免となります。詳細はこちらをご確認ください。
Q:宮城大学は修学支援新制度の対象校でしょうか
宮城大学は修学支援新制度の対象校として認定されています。参考:宮城県ウェブサイト
Q:どのようにしたら支援を受けられますか
日本学生支援機構の給付型奨学金を申請し、認定を受けることで支援の対象となります。
Q:一度支援の対象となった場合はその後支援を受け続けられるのでしょうか
支援の対象となった学生に対し、毎年経済状況及び学修状況の確認が行われます。経済状況は、家計の収入状況により日本学生支援機構が判定を行います。
学修状況は、1年間の学修成績をもとに大学で行います。経済状況、学修状況次第では、支援の増減や停止等が発生することがあります。
課外活動に関すること
Q:どのようなサークルがありますか
運動系サークルや、芸術やデザインに関する文化系サークル、パ フォーマンスや自己表現を磨くサークルなど幅広く揃っています。
詳細はこちらをご確認ください。
Q:大和キャンパス・太白キャンパスでサークルは同じですか
大和キャンパス・太白キャンパスでサークルは別団体となっています。そのため、同じ名称のサークルがある場合でも、活動内容等が異なることがあります。
Q:新しくサークルを作ることはできますか
所定の条件(活動人数等)を満たすことで新しくサークルを作ることが可能です。
その他
Q:講義が無い時間、学生はどのように過ごすことが多いでしょうか
カフェテリアやサークル室などで友人やサークル仲間と過ごしたり、図書館で勉強をする学生が多いようです。また、2018年から新設されたラーニング・コモンズで、教員や学生同士で交流を深める場面も見られます。
Q:入学後アルバイトを始める予定です。アルバイトをしながらでも講義についていくことができるでしょうか
アルバイトしている学生は大勢おりますが、学生は時間を工夫し勉強とアルバイトを両立しています。