新着情報
21.12.14
11/26 自治体向けセミナー「総合計画策定のあり方を考える研究会」を開催しました/研究推進・地域未来共創センター
11月26日、研究推進・地域未来共創センター主催の自治体向けセミナー「総合計画策定のあり方を考える研究会」を開催しました。「総合計画」とは、地方自治体が策定するすべての計画の基本となる指針で、行政運営の最上位計画です。自治体の考え方や、社会から要請される課題にいかに対応するかを示す必要があり、また、コンセンサスを得るための策定プロセスも含めて様々な工夫や配慮がなされています。この研究会は、本学の実績とネットワークを活かし、自治体職員が実務に役立つ知識や手法を学び、意見交換や交流の機会とすることを目的に企画しました。

「総合計画」策定の工夫や、各自治体で感じた現場の課題を共有する
研究会では、本学と連携協定を結んでいる富谷市、蔵王町、大和町、加美町の各自治体の担当職員から、計画策定の事例・取組内容、策定プロセスや計画の実行にあたっての課題が共有されました。その後の意見交換会を通し、以下のような共通の話題が浮かび上がりました。
- 職員自らが総合計画を策定できる意識・能力を醸成する必要性
- 市町村内外を含め、子育て世代や若者の声をいかに収集し住民ニーズを把握するか
- 総合計画の目標を、具体的な地方創生総合戦略等のプロジェクトへいかに展開できるか
- 総合計画をどのように市民に浸透させ、参加を促していくか
これらに加えて、コロナ禍での計画策定あたっては地域に出向くことが難しくなっている状況から、市民の声を集めにくくなっている点が話題に上がっています。
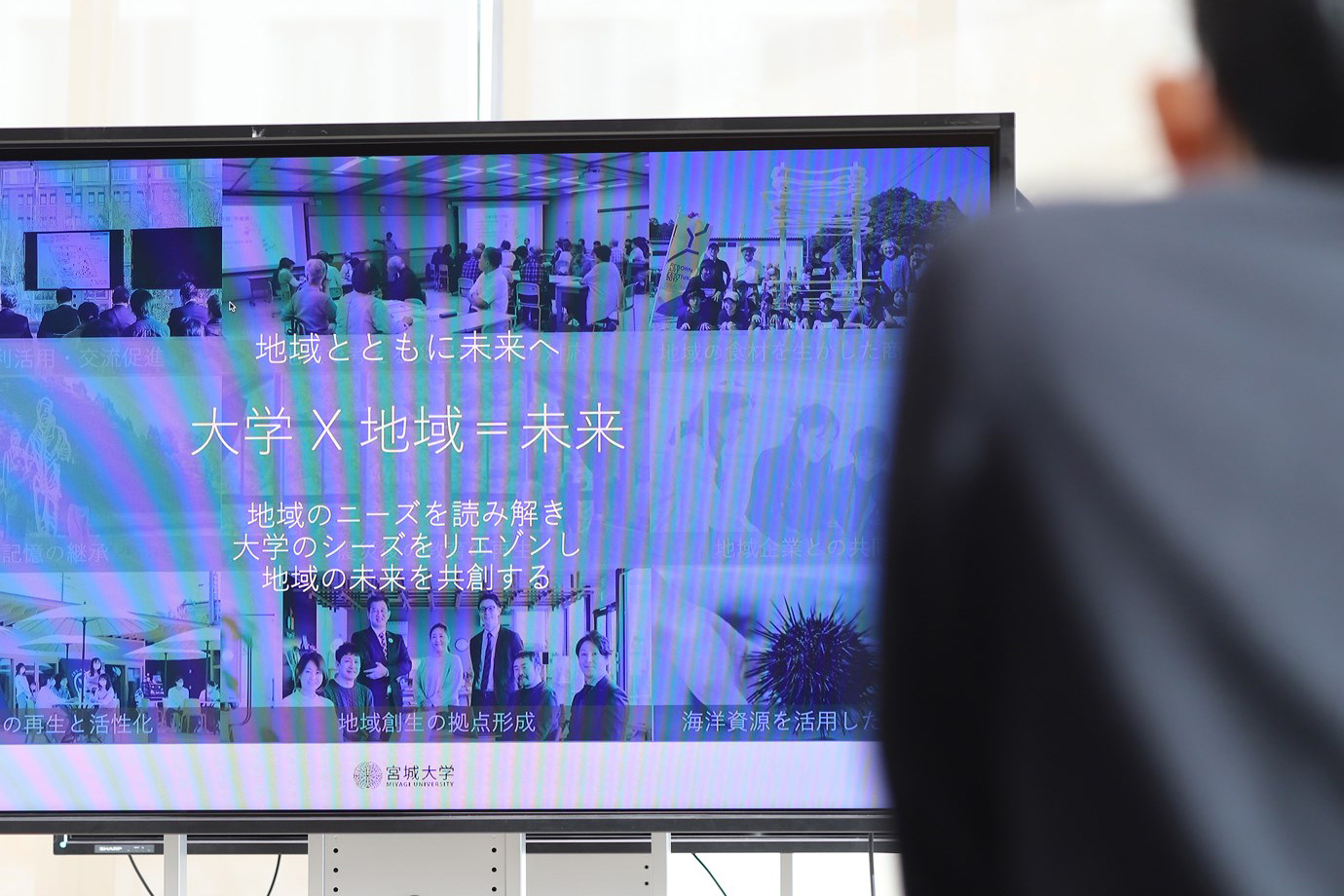
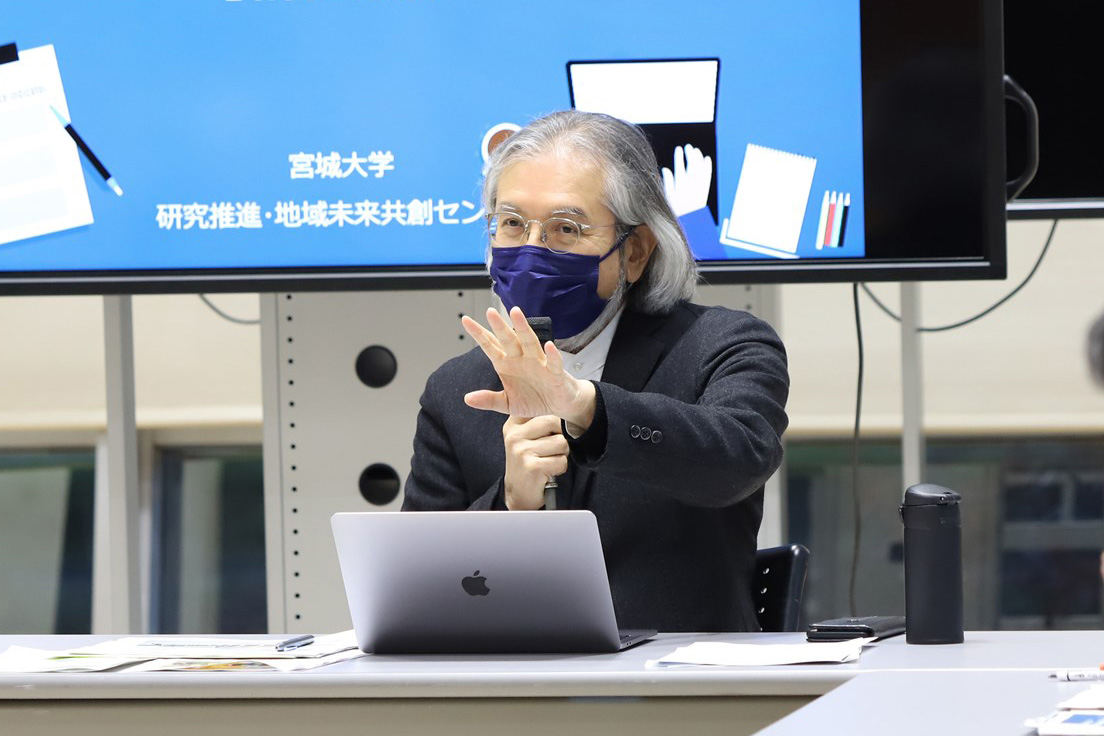





市民の参加による「共創の場づくり」が、課題を解決するきっかけとなる
研究会での議論を踏まえ、公共施設の統合や市街地復興計画、自治体の総合計画などに多く参画してきた風見センター長により、計画策定を進める上で課題を解決し得るキーワードが紹介されました。
- SDGsなど新しい時代の課題を取り入れる「先端性」
- 市民参加型での計画づくりによる「透明性」
- 次世代の市民や地域連携の促進による「持続性」
- 総合戦略等の政策と連動させることでの「実効性」
- 地域資源や地域特性を組み込んだ「独自性」
特に、本学の共創プロジェクトでも実践されたものがありますが「市民参加型での計画づくり」は、ただ意見を集めるものではなく、市民の参画を促すことで地域本来の魅力を見つけ、優れた独自の計画に発展させる取り組みとして、いくつかの課題を解決し得るキーワードとなり得るのではないか、と語りました。
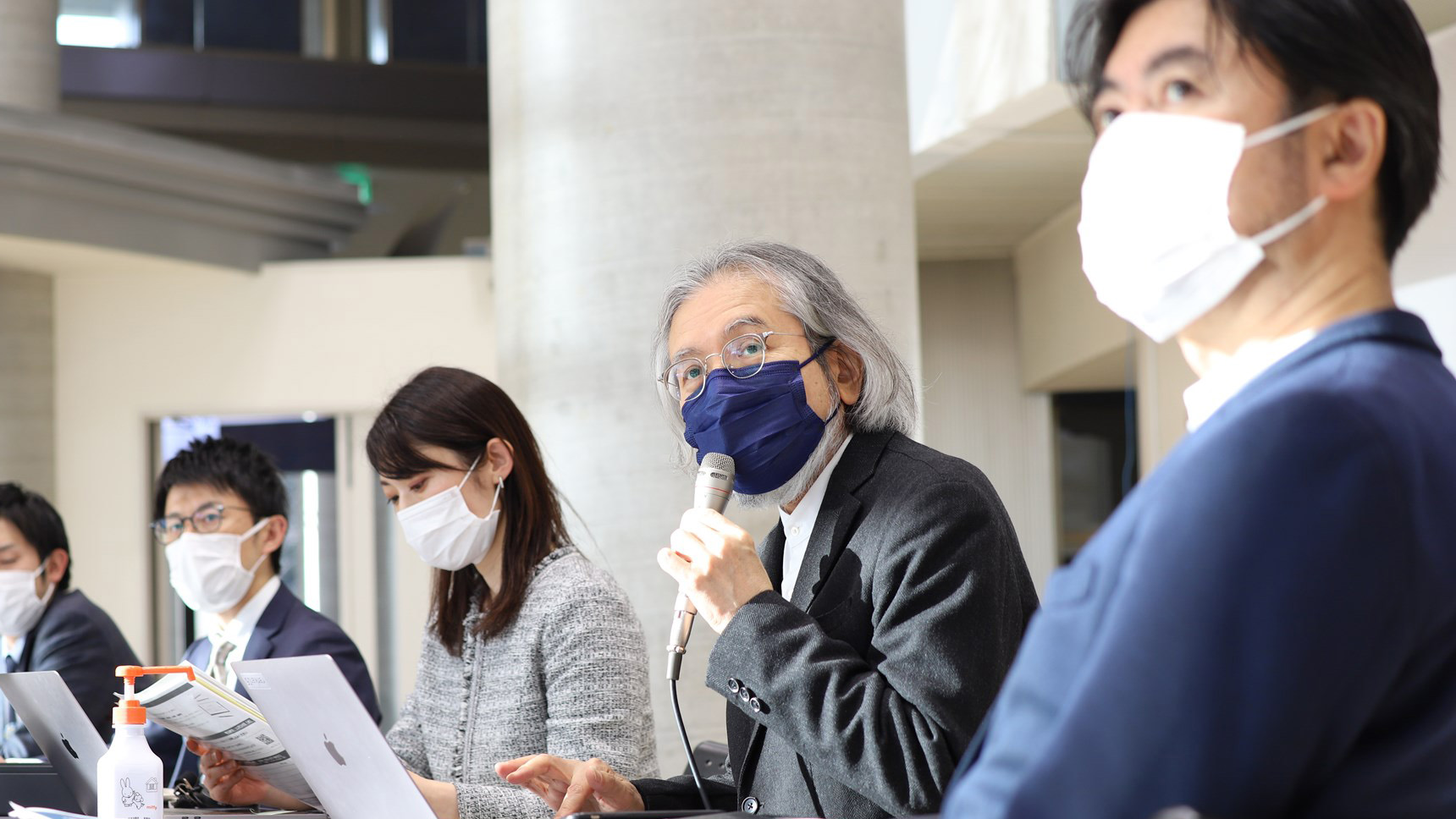
研究推進・地域未来共創センターでは、地域の企業、自治体、学術・研究機関、金融機関等との連携に取り組み、様々な共創の場を展開していきます。
宮城大学研究推進・地域未来共創センター
宮城大学の教育や研究に関わる知的財産を活用し、地域の企業、自治体、学術・研究機関、金融機関等との連携を進めながら、新たな研究開発や地域未来共創プロジェクトを推進し、真に豊かで持続可能な地域社会を実現していくために設立。本センターは、本学における看護学群、事業構想学群、食産業学群、基盤教育群の各領域及びそれらの横断的な教育・研究の成果を基に、東北・宮城の様々な地域の資源や人材を新たな発想と視座から連携し、地域未来共創を推進するプラットフォームを構築していきます。

