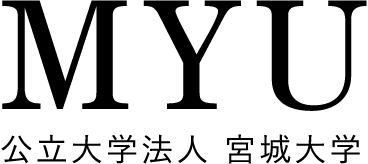新着情報
23.06.08
宮城大学の入学者選抜が文部科学省「令和4年度の大学入学者選抜における好事例」に選定されました
宮城大学の「一般選抜個別学力検査の記述式総合問題『論説』」が、思考力・判断力・表現力の評価・育成の点で他大学の参考となり得るものとして、令和4年度大学入学者選抜における好事例に選定されました。文部科学省では、令和3年度より高大接続改革や大学入学者選抜方法の改善を一層促進する観点から、他大学の模範となる好事例を調査・選定し公表しており、本学の取り組みが2年連続で選定されました。今回の調査では、延べ704の国公私立大学(短期大学を含む)の中から本学のほか東北大学や神戸大学、明治大学などの17件が選定されています。

記述式総合問題「論説」の特色
複数の教科・科目を横断して「読解」「情報分析及び活用」「表現」の力を総合的に評価
宮城大学では、2017年度の学群・学類制度の導入に伴い、入学者選抜制度改革を行いました。新しい教育課程では、知識を活用して思考し、判断し、表現する力を重視し、教科を横断した問題探究型の学びが展開されています。このような背景を踏まえ、基礎学力に加えて高等学校等での課題探究型学習の成果として「得られた事象や情報を整理・分析し(思考力、判断力)、概要にまとめ、論述する力や態度(表現力)が身についている」ことを評価するために、記述式総合問題「論説」を導入しました。



「論説」は、複数の教科・科目を横断して「読解」「情報分析及び活用」「表現」の力を総合的に評価する記述式の問題です。従来の小論文では評価しきれない、探究活動で培われた力、特に論拠を見出し、論理的に思考しまとめる力を重視しています。問題の構成は、探究活動の臨場感を出すため「ある課題に自身が直面した場合にどのように対処するか」という問いになっています。探究活動に取り組んできた方、特に資料から事実を認識し課題を整理できる能力や、立場や視点の違いによって見え方が変わることを根拠に推察できる能力を持つ方にとっては、取り組みやすい問いの作りとなるようにしています。

高等学校等での課題探究型学習の成果の評価と入学後教育への効果的な接続
今回評価されたポイントは、高等学校等での課題探究型学習の成果を評価する出題に焦点を当て、入学後の教育との効果的な接続を図った点です。以下は、選定委員会の委員からのコメントの抜粋です。
- 高等学校等での学習の成果として「得られた事象や情報を整理・分析し(思考力、判断力)、概要にまとめ、論述する力(表現力)や態度が身についている」ことについてよく考えながら出題がされている。
- 高等学校の探究的な学習の内容とつながるものであり、思考力・判断力・表現力を評価する問題として妥当である。
- 高校と大学の学びを接続させる意味においては、他大学のモデルになるはずである。
- 小論文だけを課していた従来の出題より、思考力や判断力を丁寧に評価している。
- 複数の課題文や図表等のデータを読み取り、情報を分析し、文章にまとめる力は、高校の探究的学習の成果を測るものである。
- 「論説」に求める情報を分析する力や課題を見出す力は、入学後の「基盤教育」なる教養科目において必要な課題発見・解決する学修に接続する力となっている。

笠原アドミッションセンター長は「高大接続改革や大学入学者選抜方法の改善については、多くの大学でその対応に追われているのではないでしょうか。本学の事例が、こうした対応を進める際の一助になれば幸いです。宮城大学は、引き続き時代の変化に適応しながら、高校から大学への『架け橋』となる入学者選抜を目指し、実践していきます。」とコメントしました。

アドミッションセンターについて
アドミッションセンターは、2016年4月に宮城大学における入試改革に関する事業を推進する目的で設置されました。当センターは、本学のアドミッションポリシーに即した入学者を適切に確保するために、入学者選抜の基本方針の策定、入学者選抜に関する調査研究および入試分析、入試に関する広報活動および相談、入学者選抜の円滑な実施に関する総括を行い、本学の教育研究の充実発展に寄与することを目的としています。
高大連携推進室について
宮城大学では 2019 年度に高大連携推進室を設置し、地域に貢献する人材を育成するため高校と大学の連携強化を進めています。高校生が大学での深い学びを体験するアカデミック・インターンシップや、高校における「総合的な探究の時間」の充実を図るための大学教員による指導支援、高校と大学の教員がそれぞれの立場で意見を交わす高大連携事業協議会等を展開しています。