新着情報
25.05.13
“新しい体験提供”דユニークな情報発信” 人口減少・志願者低下を突破するための 宮城大学の「高大連携+入試広報」戦略とは?
宮城大学アドミッションセンター高大連携推進室では、2023年度から高大連携 ( 高校と大学が協力して教育活動を行う ) を大幅に見直しました。主に事業構想学群を対象として、テクノロジーを活用した模擬講義など、高校生及び高校教員への「新しい体験」の提供に取り組みました。高校生が情報収集するプラットフォームで毎日更新し、学生や高校生ともコミュニケーションする「ユニークな情報発信」に取り組む入試広報施策とあわせた、宮城大学の「高大連携+入試広報」の戦略をご紹介します。

人口減少などにより飽和状態の市場と、地方公立大学特有の課題
大学全入学時代と言われる昨今、志願者数の確保はどの大学でも大きな課題となっています。特に地方公立大学は、国立大学とは比にならないほど少ない予算や人員で高大連携や入試広報を行わなければならず、通常業務も行いながら新たな活路を見出すのは難しい状況です。その中でも東北地方は、18 歳人口の減少率が極めて高いことから、志願者数確保の難易度が年々高まっており、大学における効果的な入試広報施策が求められています。
高校の進路担当者へ直接インタビュー 高大連携活動・広報活動の課題を明確化
そんな環境下であらためて見直すと、宮城大学には事業構想学群や食産業学群など他大学にはない独自のカリキュラムや教育プログラムを持つ学群があります。しかし、高校生や高校側には宮城大学の魅力をうまく伝えることには苦戦しており、高校の進路担当者へのインタビューでは「事業構想学群や食産業学群は、名前はユニークなので知っているが、具体的に何ができるのかまだ理解できていない」「学校の説明のみではなく、高校生にとって魅力的と感じられるコンテンツがあったらよいと思う」などの声がありました。宮城大学の魅力や独自性はあるものの、それが体験や情報発信を通して伝わっておらず、高大連携や情報発信の在り方が改めて問われました。
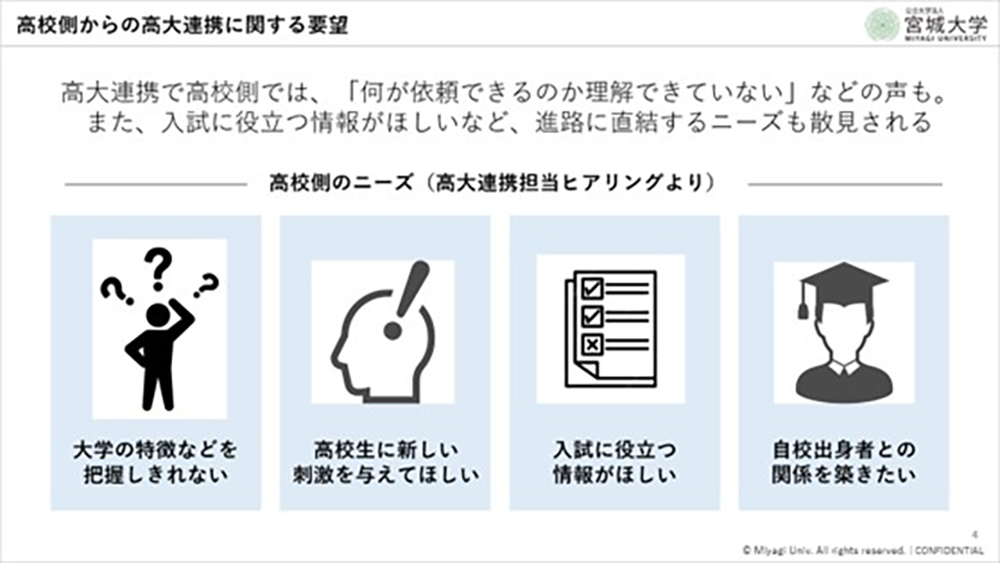
高校生に新たな発見を与える「新しい体験の提供」と「ユニークな情報発信」へ!
そこで高大連携推進室では、高大連携戦略立案の前段階として、まずは高大連携の在り方を見直すべく、高大連携推進室の部署ミッションの策定を行いました。高大連携活動とは高校生に一体何を提供すべきなのか。ディスカッション等を通し、見えてきた方向性は「新しい発見を提供する」ということでした。高校生にとって今までにない驚きになるような発見を提供できているか。高校の教員にとっても有益なコンテンツを提供できているか。その想いを込めて、部署のミッションを「高校生及び高校関係者に、常に新しい発見を提供する!」と定めました。またそのような体験や情報提供を地方公立大学の限られたリソースの中で実現していくためには、業務の効率化が不可欠であることから、業務フローの整備や学内の新たな仕組みづくりにも着手しました。
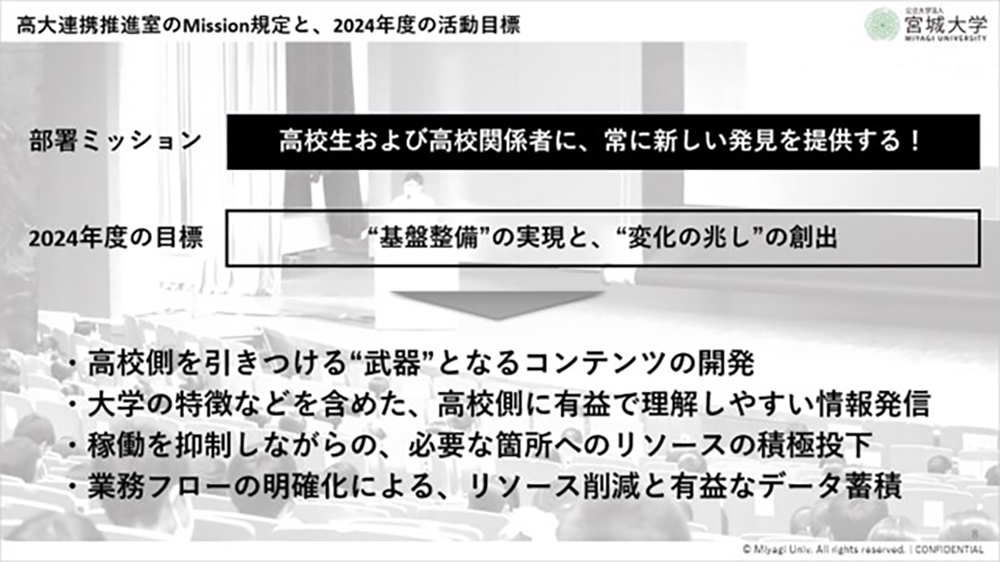
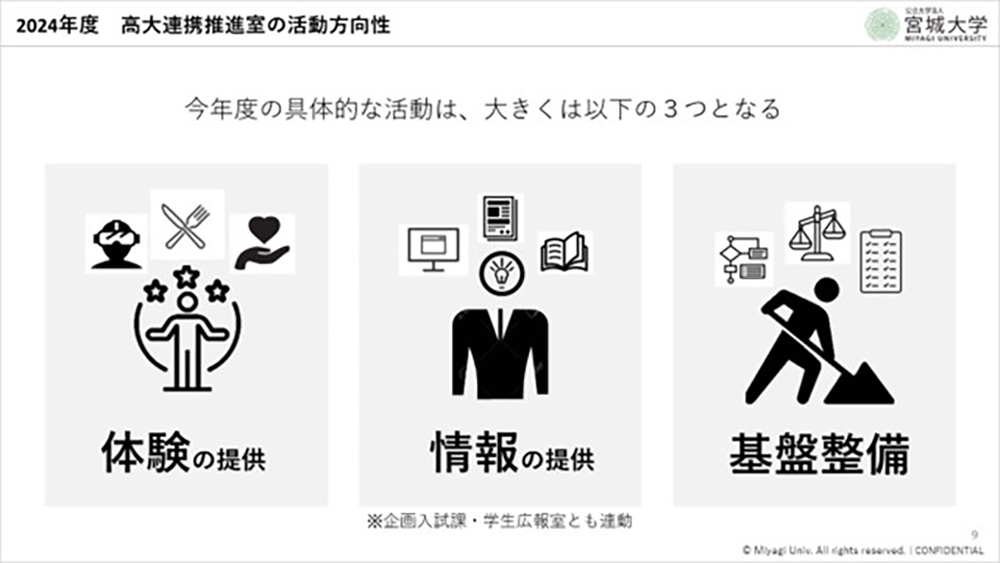
【新しい体験の提供】「未来志向型アントレプレナーシップ教育プログラム」
宮城大学事業構想学群では、高校生への新たな体験の提供として、VR やドローン、ChatGPT などの最新技術を体験しながら、課題発見・解決力や構想力を育成する実践的な教育プログラム「未来志向型アントレプレナーシップ教育プログラム」を開発しました。このプログラムでは、ドローンのプログラミングを体験し自分でドローンを動かしたり、与えられた課題を ChatGPT と対話しながら解決することで、テクノロジーの活用方法などを体験を以て学ぶほか、自分が感じている社会の課題などを、テクノロジーを活用して解決方法を模索することで、社会課題の解決に向けた心構え等も学ぶプログラムとなっています。体験した高校生からは、「プログラミングは難しい印象があったけど、実際やってみて面白いし、簡単なものから始められることが分かり、とても良いきっかけになった」「初めて触れる最新のテクノロジーを実際に体験することにより、日常生活とは異なる刺激を受けることができた」などの声がありました。※このプログラムは、JST の EDGE-PRIME Initiative の事業の一環として開発を行いました。
【宮城大学×仙台育英学園】「未来志向型アントレプレナーシップワークショップ」
【宮城大学×尚絅学院高等学校】「未来志向型アントレプレナーシップワークショップ」
MESH・ドローン・VRなど最新テクノロジーを活用した高校生向け教育プログラム「未来志向型アントレプレナーシップ教育プログラム」を過去最大規模で開催






ウェブサイトで企業や自治体と連携した取り組み・最新の情報を、魅力的に高頻度で発信
宮城大学では、2018 年度より、学内の情報の流動性を高める整備を行い、企業・地域とのコラボ事業など、宮城大学のユニークな取り組みを、ウェブサイトを中心に密度高く魅力的に発信しています ( 年間 350 件の新着発信 )。東北地方の公立大学では非常に高い水準を維持しており、品質の高い発信をベースとしたブランディングに取り組んでいます。統一感をもった広報ツールは 2021 年度グッドデザイン賞を受賞。
「宮城大学広報ツールのトータルデザイン」/2021 GOOD DESIGN AWARD
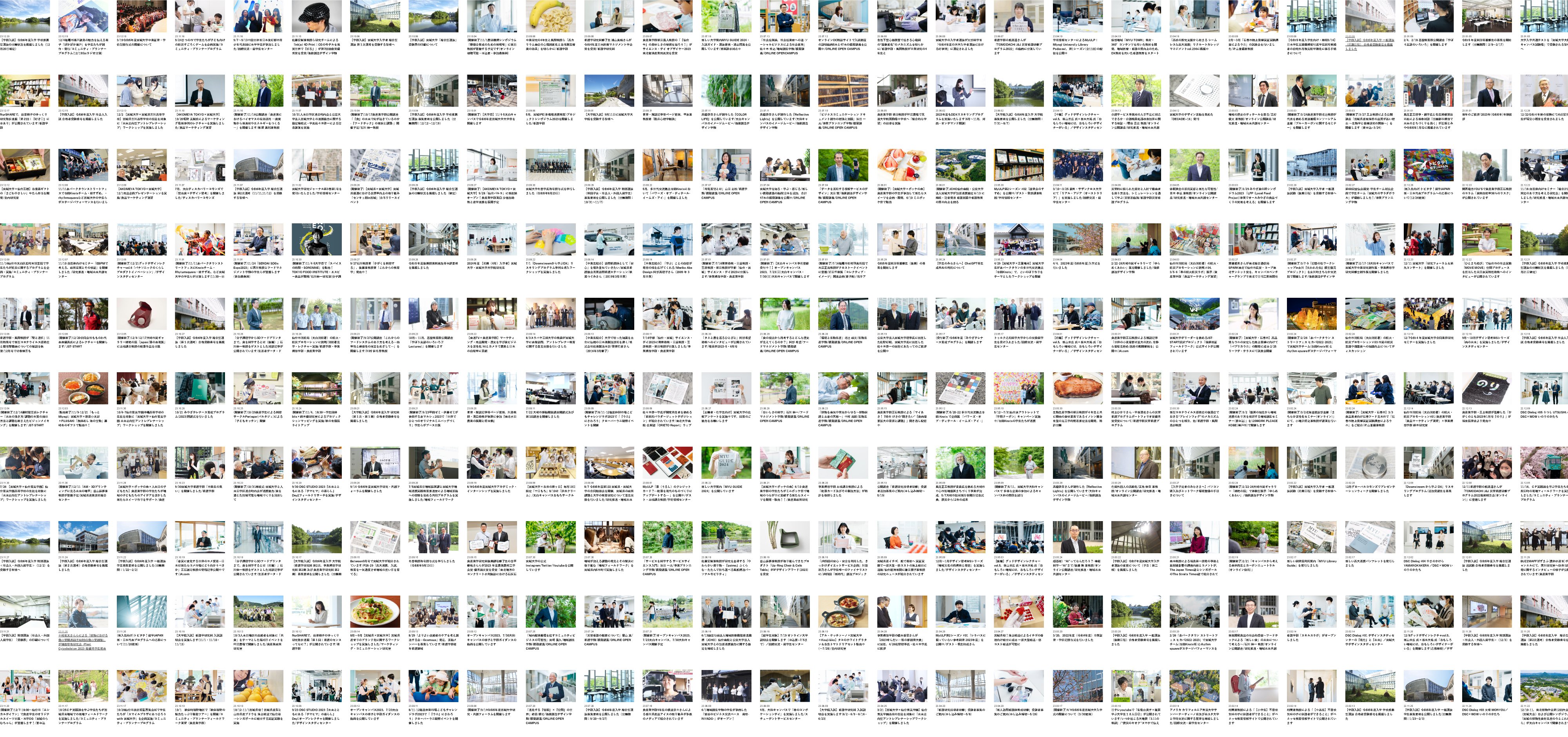
毎日更新する Twitter / Instagram
学生たちのチャレンジを応援するフレンドリーな宮城大学公式 SNS
公式 SNS は 2023 年度 6 月より運用を開始し、まだ 2 年間の運用ですが、Twitter約 3700 フォロワー(公立大学 10 位)・Instagram 約 2000 フォロワー(公立大学 16 位)規模を記録しています。SNS チームは広報職員と学生が連携し、ウェブサイトと連動した宮城大学独自の取り組みやキャンパスの最新情報を頻度高く、毎日更新しています。昨今の SNS アルゴリズムではユーザー同士の交流を重視した非常に柔軟な情報発信が効果的であることから、宮城大学のファンとなったフォロワーとは学内外問わず交流する取り組みを行っています。「助けて!宮城大学」はインターネットメディアでもニュースとして取り上げられるなど、様々な層から支持を得ました。
Instagram / Twitter / インターネットメディアニュース(参考)

学生目線での独自発信も推進:宮城大学学生広報部
宮城大学の学生によるサークル「宮城大学学生広報部」と連携して、学生目線での独自発信を行っています。Note では、チャレンジしている学生へのインタビューを掲載する「STUDENT TALK」企画を運用、その他にもキャンパスの日常を発信したり、学群ごとの合格体験記を公開しています。
宮城大学学生広報部 MSPR note

体験と情報提供以外にも、新しいチャレンジを数多く実施
高校生向けのみでなく、高校の先生方に向けた新しい体験の提供にもチャレンジしています。毎年2回開かれている宮城大学高大連携事業協議会では、宮城県内外の高校側の高大連携担当の先生方を対象に、宮城大学の活動紹介はもちろんのこと、高大連携担当の教員同士で、高校側の課題や悩みを共有し合うワークショップを実施。普段は関わりが少ない他校の教員と情報交換を行うことで、新たな発見を得られる機会提供を行いました。
今年度は更に高校との連携を強化 高校生への価値提供を拡大へ
宮城大学事業構想学群の2025年度入学者選抜における志願者数は、前年の729人から873人に増加しました。高校生向けの「新たな体験創出」にフォーカスし、高校生向けの最先端の教育プログラムを開発したことと、それを広報でスピーディーかつ魅力的に発信したことも、事業構想学群の魅力がこれまで以上に深く伝わった要因の1つだと考えています。
今年度は、昨年度までの実績を基にさらなる高校生への提供価値の拡大に向けた取り組みを検討しています。具体的には宮城県内の DX ハイスクール採択校と連携した教育プログラムの開発や、宮城県外の高校生へのアントレプレナーシップ教育プログラムの提供など、高校から大学へのシームレスな教育の実現に向けて、新たなチャレンジを模索してまいります。

| 本リリースに関するお問い合わせ先 宮城大学高大連携推進室長:高山純人 /電話:090-3759-4099 メール:takayamas@myu.ac.jp |
高大連携推進室について
宮城大学は大学の目的で掲げるように「地域社会及び世界の大学、研究機関との自由かつ緊密な交流及び連携のもと、豊かな人間性と高度な専門性、確かな実践力を備えた人材を育成することをもって地域の産業及び社会の発展に寄与する」ことを目指しています。「このようなイベントで大学教員の力を借りたい」「生徒の進路実現のために大学での学びをイメージさせたい」など、高等学校のニーズに合わせた相談を受け付けています。まずは、お気軽に問い合わせください。

