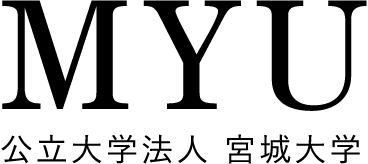新着情報
21.11.18
9月~10月、大崎市移動開放講座第4回〜第6回を開催し、閉講式を行いました
令和3年9月から10月にかけて、大崎市役所にて「宮城大学移動開放講座 第4回~第6回」を開催しました。この講座は平成19年に締結した「宮城大学と大崎市との連携協力に関する協定・連携事業協力事業」の1つとして、平成20年度より開催しているものです。昨年度はコロナ禍により開催が見送られたため1年振りの開催となりました。
(これまでの移動開放講座)
7/17 「大崎の地形と気候風土の成り立ち」(高橋 信人 准教授)
7/31 「臭い?まずい?発酵食と伝統食」(金内誠 教授)
8/21 「知っておきたい!予防したい!新型コロナウイルス感染症について」(桂晶子 准教授)



第4回講座
「SDGsと食品ロス」(9月18日)
第4回講座は、食産業学群の作田教授が「SDGsと食品ロス」と題して講義を行いました。SDGsが採択された歴史的背景を詳しく解説するとともに、生活に身近なSDGsの取り組みとして実施できる食品ロス削減の意義や、取組事例について紹介しました。

講師プロフィール
・作田 竜一 :食産業学群 教授
食の安全を確保について、「農場から食卓まで」のフードチェーンとしての食の安全を科学と行政の観点から考える中で、消費者の意識や求めるものと行政施策のギャップ、食の提供者である企業等の行動や取組を分析し、より良い対応について考えて行きます。また、農業分野の担い手不足が深刻化し、スマート農業の導入など農業が大きく変化する中で、農業分野の新たな担い手としての障害者の就労(農福連携)の取組について研究しています。
<関連>
・仙台三越で分身ロボットOriHimeを用いたICT在宅農福連携モデル実証実験を行いました
・食産業政策研究室×みやぎ生協、買い物弱者対策に「小型移動店舗」
第5回講座
「生活過程を整える~ナイチンゲールに学ぶ健康管理~」(10月2日)
第5回講座は、看護学群の木村教授が、看護学の基礎となる「ナイチンゲールの看護論」を元に、病気になる原因や、自然治癒力を高める4つの要素、近年取り上げられている「フレイル」などについて講義を行いました。学術的知見をふまえながら、コロナ禍において心と体の健康を維持するためのポイントを紹介しました。

講師プロフィール
・木村 眞子:看護学群 教授
「医療従事者のパフォーマンス」が中心テーマです。効果的にケアを提供するための技術や方法と、それを提供するために必要な仕組みをどのように作るかを、組織の視点から研究しています。
<関連>
・「国家資格とは何か 専門職看護の確立とナイチンゲールの戦い」看護学類/模擬講義
・公開講座2019「自分でできる転倒予防」(木村 眞子教授)
第6回講座
「ストレスに強くなる!原因と解消法について理論から学ぶ」(10月9日)
第6回講座は、事業構想学群の絹村講師がストレス・マネジメントの理論をもとに、ストレスについての理解を深める講義を行いました。講義の中では、実際に受講生が各自のストレスチェックを行いながら、ストレスの具体的な原因は何なのか。ストレスはどのようにすれば解消できるのか。といった疑問について考えました。
講師プロフィール
・絹村 信俊:事業構想学群 講師
実務経験の有る研究者として、ビジネスの現場で起こっている問題を踏まえつつ、学術研究を進めています。
<関連>
・大手製造業の転職経験者に関する研究論文が日本経営倫理学会水谷雅一(論文)賞奨励賞
・「会計リテラシーを身に付けよう」事業プランニング学類/模擬講義
10/9 大崎市移動開放講座 閉講式を行いました
令和3年10月9日(土曜日)に閉講式を大崎市役所で行い、受講生49名のうち3回以上受講された36名の方に、修了証と宮城大学からの記念品が授与されました。
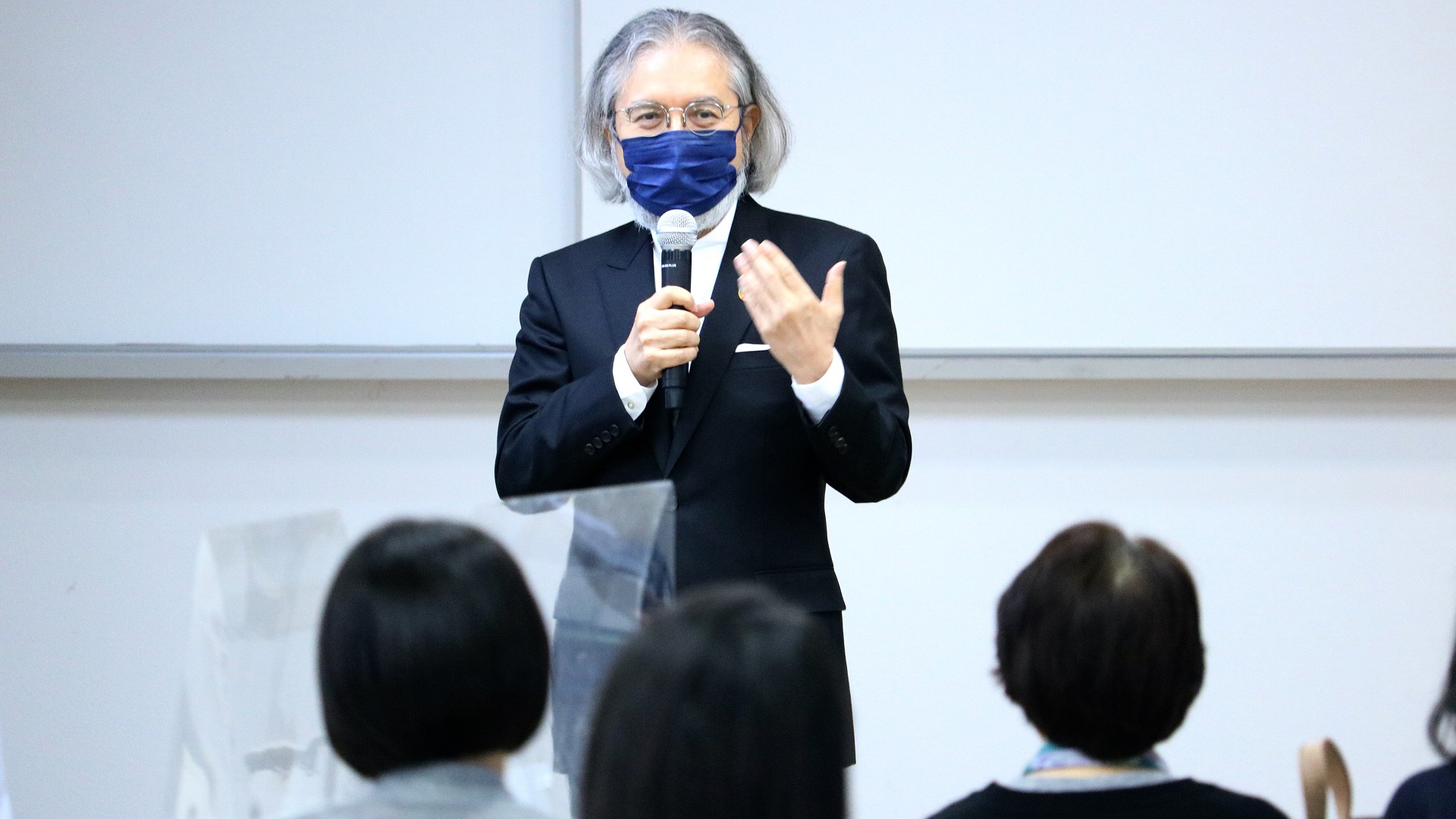
閉講式では、大崎市長より「修了生の皆さん、修了おめでとうございます。宮城大学とは平成19年から連携した活動を行っており、本講座以外でも大崎市のまちづくりの様々な場面でご協力をいただいています。これからも市民の皆さんが安全に豊かに暮らせるまちづくりに努めて参ります。」との挨拶がありました。これを受けて風見センター長より、「コロナ禍の中、本学の移動開放講座にご参加いただいた皆さまには、改めて御礼申し上げます。宮城大学研究推進・地域未来共創センターでは、大学における研究活動を前進させると共に、その研究シーズを地域の未来のために還元する活動を展開しています。この講座では、本学の研究シーズの一部を受講生の皆さんにご紹介しましたが、これを機により多くの方に本学について興味関心をお寄せいただきたいと思います。」との挨拶がありました。
大崎市・宮城大学連携協力事業「移動開放講座」
「宮城大学移動開放講座」は平成19年に締結した、宮城大学と大崎市との連携協力に関する協定・連携事業協力事業の1つとして、平成20年度より開催しているものです。本講座は大崎圏域1市4町の住民及び大崎市が「大崎定住自立圏形成協定」を締結している色麻町、加美町、美里町、涌谷町の住民の皆さまにもご参加いただける講座です。今年度も本学の教育・研究活動の成果を大崎地域に還元できるよう、看護学群、事業構想学群、食産業学群の教員がオムニバスで全6回の講座を行います。
宮城大学研究推進・地域未来共創センター
宮城大学の教育や研究に関わる知的財産を活用し、地域の企業、自治体、学術・研究機関、金融機関等との連携を進めながら、新たな研究開発や地域未来共創プロジェクトを推進し、真に豊かで持続可能な地域社会を実現していくために設立。本センターは、本学における看護学群、事業構想学群、食産業学群、基盤教育群の各領域及びそれらの横断的な教育・研究の成果を基に、東北・宮城の様々な地域の資源や人材を新たな発想と視座から連携し、地域未来共創を推進するプラットフォームを構築していきます。