新着情報
22.03.14
看護学研究科修了生の千葉栄子さんが、日本公衆衛生看護学会の優秀論文部門で学術奨励賞を受賞
宮城県大崎市の保健師として活躍する千葉栄子さんは、社会人選抜で看護学研究科に入学、主研究指導教員の桂晶子准教授のもとで修士論文をまとめ、2017年3月に修了しました。このたび、修士論文を再編し投稿した論文「子ども虐待ハイリスク家族に対する市町村保健師の関係機関との連携の取り組み」が、公衆衛生看護学の進歩に重要な貢献をしたものと認められ、日本公衆衛生看護学会において2021年度学術奨励賞(優秀論文部門)を受賞しました。
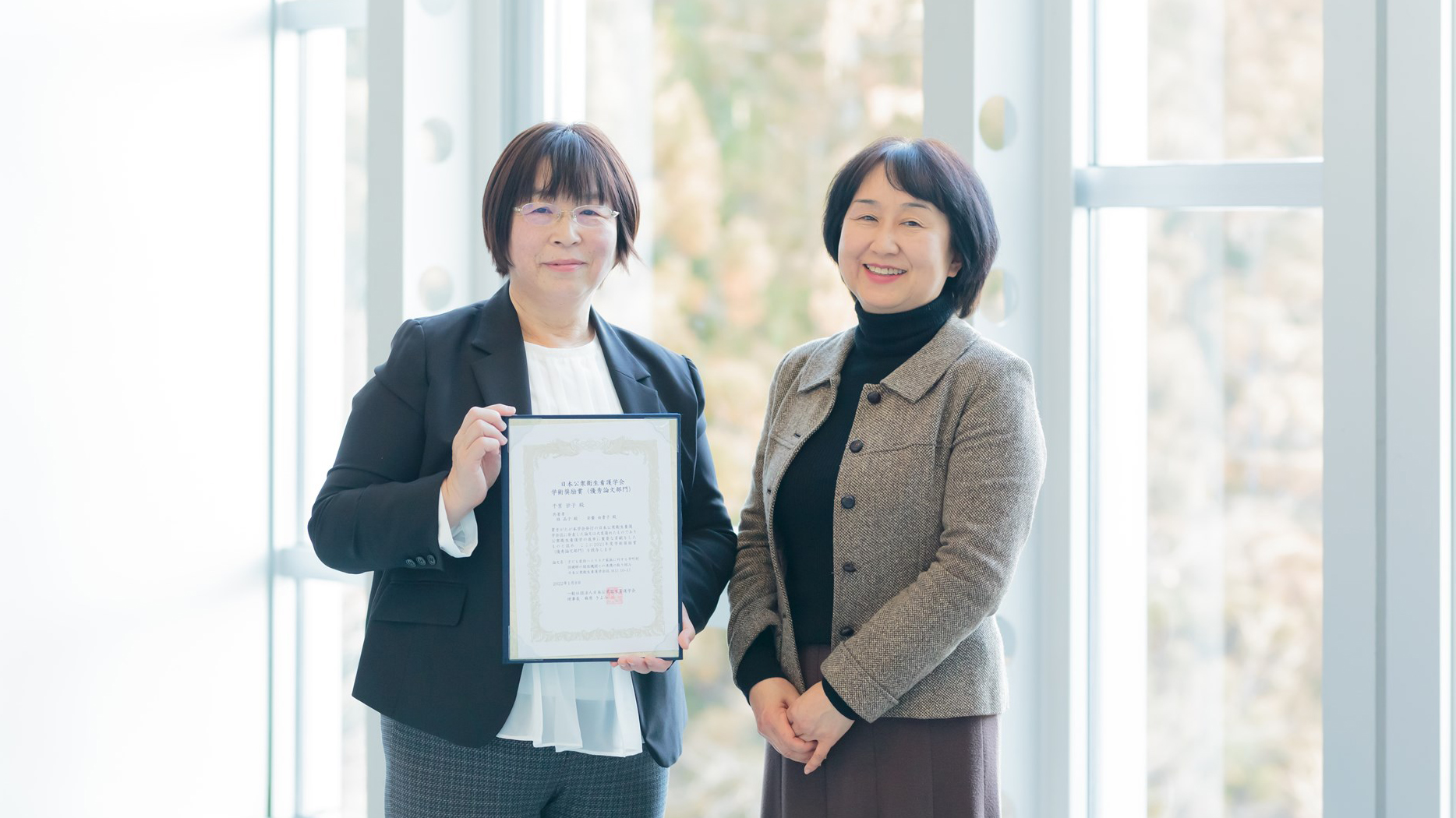
市町村に勤務する保健師は、子ども虐待予防・早期発見において重要な役割を担っている
児童相談所における子ども虐待相談は増加の一途をたどり、2021年は20万件を超えています。虐待による死亡時の年齢は0歳児が最も多く、主たる加害者は実母が最も多いと報告されています。子ども虐待の社会問題化を背景に平成12年には「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、平成16年の児童福祉法の一部改正では、市町村を児童に関する一義的な相談支援機関と位置付け、要保護児童の通告先に市町村が加えられました。

その中でも、市町村に勤務する保健師は、母子手帳交付から妊婦と関わり、出産後は新生児訪問や乳幼児健診等の母子保健事業を介して養育の状況を確認できるため、子ども虐待ハイリスク家族を早期に把握できる立場にあります。
保健師は、ハイリスクだと判断した家族に対しては、育児相談や家庭訪問等様々な機会・手段を用いながら母と信頼関係を築き、家族調整や対象者に合わせた個別支援を継続的に行っていきます。これらの活動では、医療機関や保育所といった関係機関との連携が不可欠であり、保健師が核となって課題解決のために調整的な役割を担うことが多くあります。
保健師が「どのように関係機関と連携し支援を行っているか」連携の質が求められている
子ども虐待を防ぐためには、緊急性や高度な専門的対応が時に求められます。しかし、処遇困難な家庭への支援、関係機関との連携・調整に困難感を抱く保健師は少なくありません。これは、養育者の養育能力上の問題や心身の不調、支援拒否への対応等、長期にわたる支援の継続が予測される事や保健師の業務が多岐にわたり連絡や調整等に多くの時間を割けない現状がある事等が背景にあると考えられます。そのため、現状の業務の中で、質を落とさずに効率的で効果的な連絡調整を模索していくことが必要となっています。
本研究は、子ども虐待ハイリスク家族に対して、「保健師がどのように関係機関と連携して支援を行っているか」を、子ども虐待ハイリスク家族に対する支援の経験を持つ保健師を対象に、一人一人と面接を行い、面接の逐語録をデータとして分析することで、保健師の関係機関との連携に関わる具体的取り組みを明らかにするものです。
「下地を整えつなぐ」「虐待予防に向けた協働支援」などの取り組みを抽出
今回面接を行った保健師には、関わった事例を想起し、自身が行った連携の取り組みを語ってもらいました。その語りから、実践に活かせる行動レベルの要素を抽出し、カテゴリーに分類しました。
例のひとつとして、母親に対しては社会資源を利用するメリットや利用のし易さを説明し、一方、関係機関(社会資源)には事前に母親の特性や状況を説明するなど、双方に対して「つなぐための下地調整」を丁寧に行っていました。つまり、関係機関への単なる紹介ではなく、母親と社会資源が確実につながり円滑に支援が提供されるよう「下地を整えつなぐ」取り組みを行っていたことを示します。

また、産後の養育能力不足を予想し必要な支援を出産前から関係部署と協議したり、母子の情報が速やかに届く体制を整えたりするなど、「問題発生に備え先回りして(関係機関と)手を組み支援環境を整える」取り組みを行っていました。これは、保健師が予防的視点を発揮して「虐待予防に向けた協働支援」を行っていたことを示します。
子ども虐待は、家庭の中で起きることが多く予防と早期発見が非常に重要です。発見時は即座に支援を行わなければならないことも多いため、日ごろの保健活動のなかで関係機関との信頼関係の構築を意識しておく必要があります。また、子ども虐待ハイリスク家族への支援は困難感を伴う業務であるため、支援者に対するサポートも必要です。関係者間の互いのサポートや信頼関係によって連携が促進され、情報共有や役割分担がスムーズとなり、より良い支援につながって行くと考えます。

千葉さんは「虐待を受けて育った子どもは、心身の影響が大人になってから表出する場合もあり、人生に大きな影響を及ぼすことがわかっています。虐待を防止し子どもたちが健やかに成長できるためには、地域の中にどのようなサービスや資源を整えればよいのか、必要な環境はなにか、関係機関と連携を図りながら今後も考えていきたいと思っています。」とコメントを寄せました。

研究情報概要
- 受賞名:2021年度 日本公衆衛生看護学会 学術奨励賞(優秀論文部門)
- 論文名:子ども虐待ハイリスク家族に対する市町村保健師の関係機関との連携の取り組み。日本公衆衛生看護学会誌 9巻1号pp。10-17, 2020。
- 受賞者:千葉栄子(大崎市松山総合支所 保健師)
- 共著者:桂晶子(宮城大学看護学群)、安齋由貴子(宮城大学看護学群)
虐待防止の実践に役立つ保健師活動の知見の蓄積が求められる中、子ども虐待ハイリスク家族に対し、保健師がどのように関係機関と連携し支援を行っているのかを明らかとした研究です。質的帰納的な分析が丁寧に行われている点、将来の実践への適応可能性を有する論文であることなどが評価されました。
日本公衆衛生看護学会-学術奨励賞(優秀論文部門)
日本公衆衛生看護学会は、公衆衛生看護の学術的発展と、研究・教育及び活動の向上と推進をめざし、国民の健康増進と社会の安寧に寄与することを目的とし設立されました。会員数は2,000名を数えるほどになりました。学術奨励賞(優秀論文部門)は、日本公衆衛生看護学会誌に掲載された論文について、独自性、得られた知見の発展性、論文の一貫性と完成度、論文の公衆衛生看護学及び公衆衛生看護実践への貢献度などから選考されるものです。 (公式サイトより抜粋、一部改変)

