新着情報
19.12.19
看護学群の霜山真講師が日本呼吸ケア・リハビリテーション学会「医療の質特別賞」受賞
看護学群の霜山真講師は、ICT(情報通信技術)を活用した看護支援システムの開発や看護介入プログラムの構築、またそれらの効果検証に関する研究を行っています。このたび “非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)を受ける慢性呼吸不全患者へのセルフケア能力の獲得支援”をテーマとした研究活動が日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の「医療の質特別賞」受賞しました。
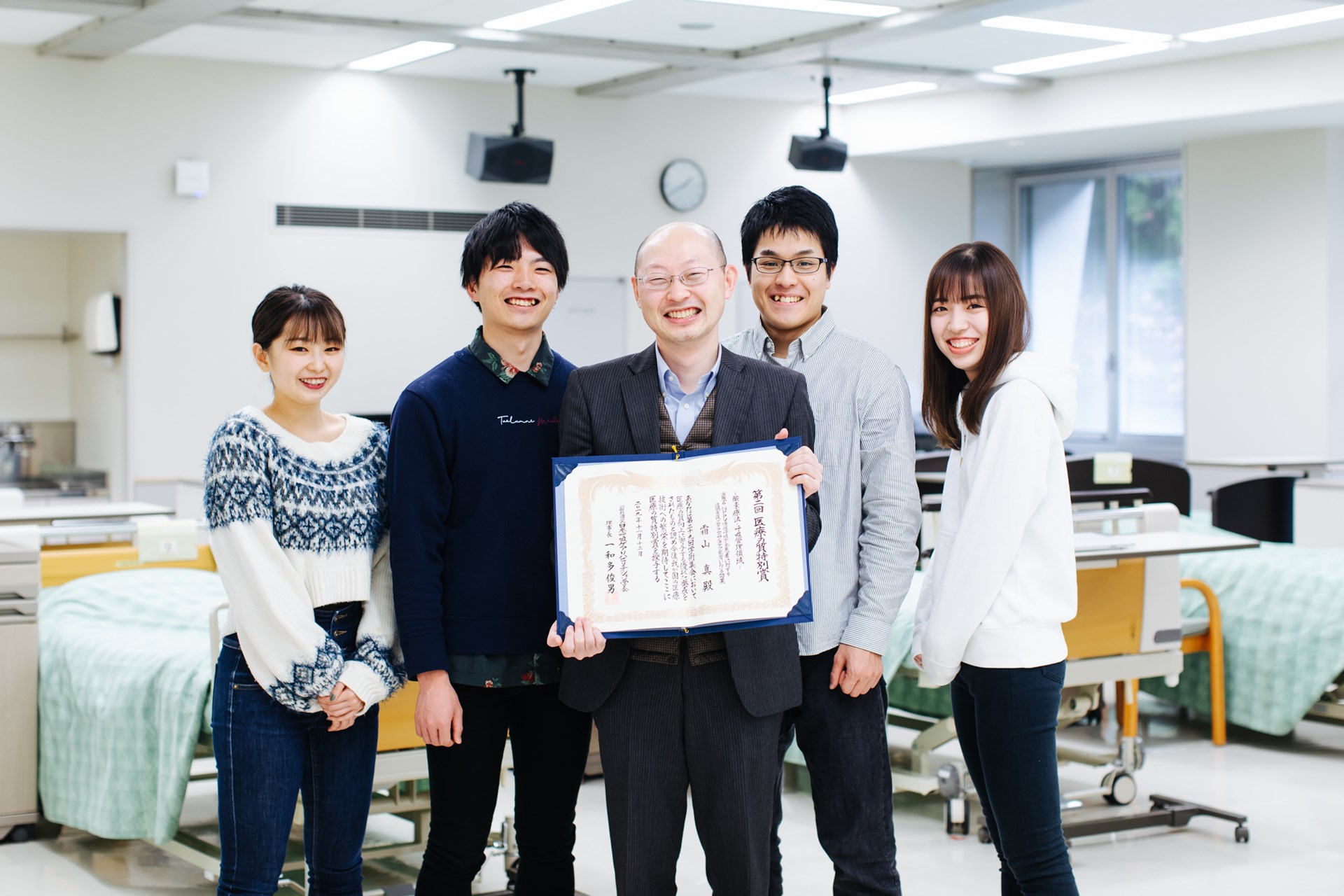
慢性呼吸不全のセルフケアに寄与する遠隔看護の可能性を実証
“慢性呼吸不全”とは、大気中から酸素を取り入れて体内でできた二酸化炭素を体外に放出する肺本来の働きが果たせない状態が、1カ月以上続く症状です。重症化すると身の回りのことをするだけで息切れを感じて、日常生活が困難になるほか、心不全などの原因となる場合があります。この慢性呼吸不全の治療のひとつに“非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)”があります。これは、重度の慢性呼吸不全患者を対象に、身体への侵襲(ダメージ)のない特殊な⿐マスクや⿐⼝マスクなどを⽤いて、設定した圧力で肺の中に空気を送り込む治療法です。
“NPPV”を受けている患者の多くは呼吸状態が安定しない中で、自己管理をしながら生活をしています。また、症状の急な悪化などにも備える必要があります。今回評価された霜山講師の研究は、このようなセルフケア能力が強く求められる患者が、日常生活の中で、セルフモニタリングや症状への対処行動など自己管理を主体的に行い、心身の状態に応じてストレスなく行えるよう支援する「遠隔看護システム」の開発と効果検証です。



セルフケア能力に対する効果については、霜山講師が開発したタブレット用の遠隔看護システムを用いて、12週間の試験によって検証しました。試験前に被験者のセルフケア能力を得点化して低値グループと高値グループとに分けたうえで、遠隔でのモニタリングによる体調の可視化や、健康相談も適宜実施。被験者のセルフケア能力得点の変化や群間での変化量に着目した結果、セルフケア能力値の低かったグループにおいて健康管理への関心および総得点が向上したことがわかりました。これらの検証の結果、NPPV慢性呼吸不全患者に対し、遠隔看護システムがセルフケア能力を維持・向上させる可能性が示唆されました。
ICTを活用した遠隔看護の実践に向けて
日本の地域社会では、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最後まで続けることができるような住まい・医療・介護・予防・生活支援のシステムが求められています。「遠隔看護」は、健康管理を必要とする患者の健康増進を目的として、ICTなど通信技術を用いて、バイタルサインデータを収集し、健康状態の把握とともに的確な健康相談や指導の機会を提供するシステムです。現在では、遠隔看護システムは、患者との双方向のコミュニケーションにより患者の抱く不安を解消することにもつながることも知られており、今回の研究のように、実践的な取組が広がっています。

霜山講師は、今後は遠隔看護の診療報酬化を目指してその他の呼吸器疾患患者やがん患者等においても検証を行っていくとともに、臨床現場で医療従事者が使用しやすい遠隔看護システムと効果的なプログラムの開発を行い、遠隔看護の実用化に向けて活動していく予定です。
※本研究はJSPS科研費16K20757、19K10853の助成を受け、実施した調査の一部です。
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、医療の質特別賞
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会は、学術集会の開催や学術誌の発行、研究、調査、教育活動において、呼吸ケアおよび呼吸リハビリテーションに関する医学医療の発展に貢献することを目的として設立された学会です。「医療の質特別賞」は、その学術集会の際に寄せられるすべての一般演題の中で、医療の質の向上に寄与する優れた発表を行った学会員に対して授与されています。
研究者プロフィール
成人看護学を専門分野として、ICTを活用した看護支援システムの開発や看護介入プログラムの構築を行い、効果検証に関する研究を行っています。
・霜山 真 (しもやま まこと):看護学群講師

