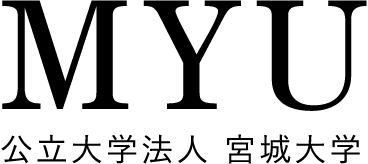新着情報
21.04.27
震災復興とブランド羊肉の開発/食を通したSDGsへの貢献,循環型の動物生産/食産業学群 大竹 秀男 教授
食産業学群 大竹 秀男 教授は,草地学,土壌動物学,ダニ学を専門分野としており,東日本大震災後の南三陸町の復興に向け,NPO法人さとうみファーム(現在さとうみリファイン株式会社)と共同でブランド羊肉の開発し,羊と共に多世代が地域の資源を活かす場の創生に日々取り組んでいます。
2011年の震災後,大竹教授はボランティア活動として,石巻のどぶさらいや亘理町のイチゴハウスの設置の手伝いなど大学を挙げて復興に携わってきた中で,復旧作業に携わっていた方々が「羊で復興に携わりたい」という要望に応え,本格的にブランド羊肉の開発に乗り出しました。
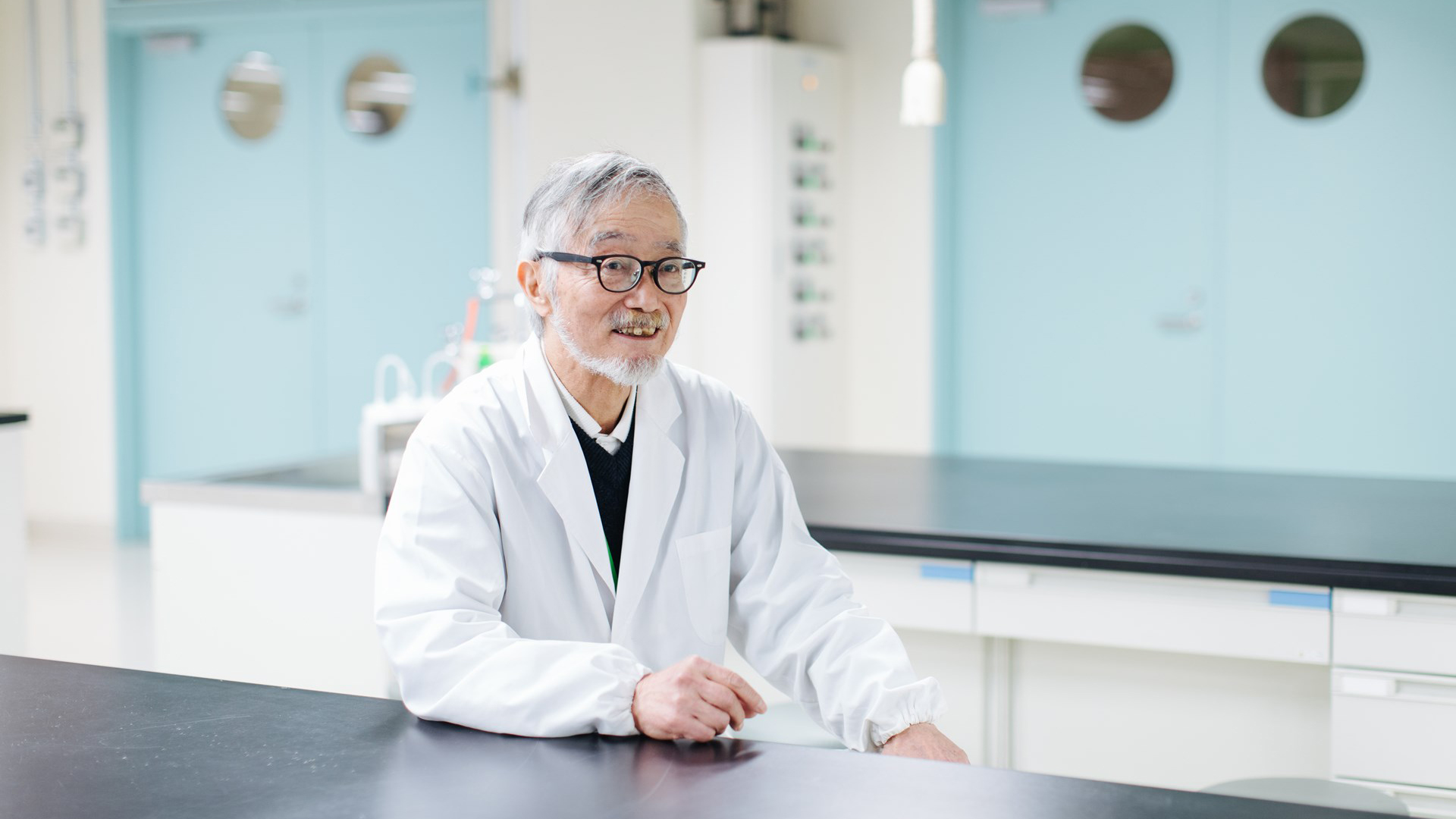
餌から取り組むブランド羊肉事業「塩」「ミネラル」多く含むワカメサイレージを活用
世界的に有名な羊肉と言えば,フランスのプレ・サレ,オーストラリアのソルトブッシュラムなどがあります。これらに共通のキーワードは,「塩」「ミネラル」です。南三陸町は,ワカメの生産が盛んで,震災後も速やかにワカメ生産が始まっている状況でした。大竹教授は,めかぶの収穫作業をボランティアとして手伝った際に,大量の“ワカメの茎”が捨てられるのを見て,「羊にこれを食べさせたら,美味しい肉になるのではないか」と考えました。

2013年12月30日羊の引っ越しの準備

冬の寒い中でのめかぶ採り

羊の放牧

2018年8月1日NHKあさイチ
ワカメの茎を実際に羊に食べさせたところ,生でも喜んで食べることがわかりました。ただし,生のワカメは採れる時期が春先に限られ,そのまま置くとすぐに腐ってしまいます。大竹教授は,1年中これらの飼料を保存できるようにするために,ワカメを含む作物をサイロに詰め,乳酸発酵させた「ワカメサイレージ」を開発しました。これにより,1年中必要な時にワカメを羊に与えることかできるようになりました。
※この活動は,ブランド化の1歩として,2018年8月にNHKテレビで「南三陸産マトン」として紹介されました。
おいしい羊肉をみなが食べられるように

ワカメサイレージを与えた羊肉は,羊臭さがないこと,コクがあり美味しいこと,柔らかくジュウーシーであることなどといった味の特徴があり,これまでの羊肉の印象とは異なり羊肉が苦手な人にも非常に愛されるおいしいお肉となりました。しかし,美味しいお肉を作っても,羊の頭数を増やさないとみなさんのお口には入りません。羊は,基本的に放牧(放し飼い)で,草なら何でも食べると思われがちですが,実はそんなことはないのです。人にも好き嫌いがあるように,羊にも好きな草と嫌いな草があるのです。羊の頭数を増やし,安定して供給するために,良い土地の確保や,羊の好きな草の多い放牧地の開発に現在も取り組み続けています。

大竹教授は「広い放牧地で,羊の行動を調査したり,牧草の成長を調査したり,自然の中での研究は気持ちをリフレッシュしてくれます。この研究は,陸と海との循環型のモデルと考えています。これからも,食を通して,SDGsに貢献できるよう,循環型の動物生産についての研究を深めていきたいと考えています。」とコメントを寄せています。
さとうみリファイン株式会社について
牛や羊などの飼料を製造・販売しております。商業的に利用されていない南三陸の海洋資源と藁とを独自の技術により発酵させることで,牛や羊などが好む芳醇な香りの飼料を生産しております。また,海洋資源は栄養を豊富に含むため,飼育された羊はしっかりとした肉の味わいになります。(公式ウェブサイトより引用)
研究者プロフィール
・大竹 秀男:食産業学群 教授
草地学,土壌動物学,ダニ学を専門分野として,廃棄ワカメと地域資源(稲わらなど)を飼料としてブランド羊肉の創生を図っています。また,昆虫の飼料化として,イナゴを採卵鶏に給与しその卵質に及ぼす影響を研究しています。
<関連>
昆虫の飼料化でタンパク源の自給率を向上させます(シーズ集)