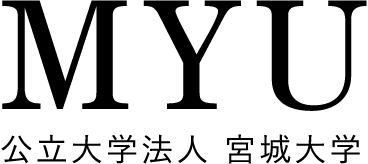新着情報
21.10.12
野菜の栽培を通して学ぶ食材生産の現場/食材生産・加工実習Ⅰ/食産業学群
食産業学群2年生の必修科目「食材生産・加工実習Ⅰ」では、食材の生産、加工方法の学びを深めるため、食資源開発学類、フードマネジメント学類の両学類とも植物性・動物性食材の生産実習や、野菜・果物の加工実習をします。そのうち植物性食材の分野では、旗立農場の畑を使って野菜を栽培する生産実習を行います。

畑での実践を通して、食の生産に関わる専門知識を学ぶ
この生産実習では、学生が5~6名のグループに分かれて、何を栽培するかを事前に相談し作付計画を立ててから栽培を開始します。ただしセメスター制のため、「前期(4月~8月)のうちに収穫でき、かつ食べる野菜であること」が条件で、期間内に収穫できるよう適切な作付計画をたてることが求められます。


例えば、夏野菜の代表であるスイートコーンの播種(種まき)適期は、仙台では5月中旬頃。しかし、この頃に播種すると収穫は8月後半になってしまい実習の条件が満たせないため、播時期を早めて4月に播種(種まき)する計画に修正が必要です。そうすると、今度は4月は気温が低いためビニルをトンネル状に覆い保温して栽培するトンネル栽培をする必要があります。この他にも、栽培計画を立てる際、肥料はどの種類をどのくらいの量使えばよいのか、殺虫剤を使うとするとどの農薬をどのタイミングでどの濃度で散布しなければならなのかなどを調べなくてはなりません。このように、品質のよいスイートコーンを生産するためには非常に多くの専門知識が必要となることに気づきます。






期間中、学生自身の手で畑の管理も行っていきますが、実際に畑で栽培してみると雑草の生命力のすごさに驚かされることも。定期的に管理しないと、あっという間に野菜は雑草の中に埋もれてしまいます。現在は除草剤を使って雑草防除することが中心ですが、世界では有機農業への取り組みが進んでおり、日本でも「みどりの食料システム戦略」が策定され、2050年までに化学農薬の使用量(リスク換算)を50%低減することが目標となっています。取っても取っても生えてくる雑草との格闘を通して、有機栽培の大変さや技術の高さ、除草の重要性などを体験することも、実践を通した学びのひとつです。


今は様々な情報を簡単にインターネットから得ることができ、わかったつもりになってしまいますが、この実習を通して実際に畑で汗をかき、育て食することで、あらためて先人たちの苦労に思いをはせると同時に、近代農業の栽培技術の発展、作物の生育特性など、食の生産に関わる専門知識を学ぶ必要性を感じることができます。

※10/11追記、収穫したコーンは無事に出荷いたしました。


食材生産・加工実習Ⅰ
食産業学群の2年生を対象とした前期開講科目です。動物性食材では、牛肉、豚肉、牛乳および自給飼料の生産を、植物性食材では、主要作物および蔬菜の生産を中心に現場における実習を体験することで、それぞれの基本的な生産方法の理解を深める実習です。生産したそれぞれの食材の食味、農畜産物の加工を通して、食材の特徴を理解すると同時に、食材の利活用を考えます。農産物の国際基準となっているグローバルGAP認証についても学びます。
指導教員プロフィール

左から、中村教授、鳥羽講師
・中村 聡(なかむら さとし):食産業学群 教授
家畜の飼料や甘味料のシロップ原料のほか、バイオマスエネルギー資源として期待されているマルチな作物「スイートソルガム」について、その能力を最大限に発揮できる栽培法の確立を目指して毎日研究しています。
・鳥羽 大陽(とりば たいよう):食産業学群 講師
より良いイネの品種改良を目指し、日々イネを理解することに研鑽しています。作物の持つ生命力, そのポテンシャルを解明し, 人類のために生かすことを目指します。
<参考>
米どころ宮城の水稲生産を実践で学ぶ“田植え実習”を実施しました/植物性食材生産実験実習I /食資源開発学類
小学生を対象としたプログラム, ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~「お米博士になろう〜大学のお米研究最前線〜」を太白キャンパスで開催しました/食産業学群 鳥羽研究室・赤澤研究室