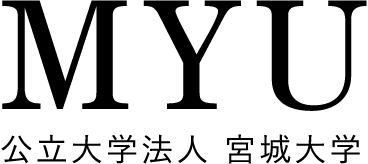新着情報
21.11.15
収穫の秋、水稲生産を実践で学ぶ“稲刈り実習”を実施しました/植物性食材生産実験実習II /食資源開発学類
食資源開発学類では、将来に向けた持続可能な食材生産と、新たな食資源の開発について考えるために、食材の生産を多角的に学びます。「植物性食材生産実験実習II」は3年次後期の選択科目で、水稲および、蔬菜類などの園芸作物の生産法を実際に体験する実験実習です。3年次に開講される講義「植物性食材生産学」で理論を学び、その知識を背景として, 1年を通して学生自らが作物の栽培を行うことで理解を深めます。
10月8日、18名の学生が太白キャンパス内の水田で稲の収穫を行いました。

「稲刈り実習」を通じて食材生産の成果を体感し、これからの農業を考える
春から夏にかけて行われた「植物性食材生産実験実習I(前期開講)」では、学生自ら水稲の種子を蒔き、苗を育て、田植えを行い、水田の栽培管理を行ってきました。稲がよく実った豊の秋を迎え、お米の重さに耐えかねて首を垂れる稲穂を見ることは、作物生産の成果を実感する瞬間です。「植物性食材生産実験実習II(後期開講)」では、稲を1株ずつ丁寧に鎌で刈り取ります。刈り取った株は10株程度をひとまとめ(一把)として、麻の紐でしっかりと結び、ずっしりと重い稲の束を担いで、乾燥のために干していきます。






この実習ではこれらの作業をあえて手作業で行います。鎌で株を刈り取る作業は、少しの油断で自分の指まで傷つけてしまうため危険を伴います。また、株を刈るためには、その根元まで体を屈める必要があるため、まるで何回もスクワットを繰り返すようなキツイ作業です。刈り取った稲を束ねて結え、担いで運ぶ作業により、着ている作業着はキタナイ状態になります。「コンバイン(稲を刈り取る機械)が出てきて、残りの稲は全部刈り取ってくれないのですか!」と作業の途中での学生からの声も。

農業機械の普及により現在の収穫作業は、その効率性が数十倍改善されており「キケン、キツイ、キタナイ」とみなされていた作物生産は、ロボット技術やICTなどの最先端技術により「感動、かっこいい、稼げる」と変わってきていることを学生たちは知識として知っています。今回の実習は、学生自身がこれらの変化を実践的に体験することで、これからの農業を考えることを狙いとしています。※食資源開発学類の学生は、生産をより「稼げる」方法にする学びを目的とした講義と実験実習「付加価値食材生産法・付加価値食材生産実験実習」を同時期に学んでいます。

たわわに稔った宮城ブランド米、その「収量構成要素」を解析して
さらに美味しいお米の栽培方法を考える
宮城県を代表する銘柄「ひとめぼれ」や有名ブランド米「だて正夢」、ずんだもちにもよく使われる糯米「みやこがねもち」、これら米どころ宮城を代表する銘柄を含む7品種を収穫しました。「お米をどれだけ生産することができたか」すなわち玄米収量は、4つの要素、いわゆる収量構成要素にわけることができます。
玄米収量 = 「単位面積当たりの穂数」 x 「1穂あたりのもみ数」 x 「登熟歩合」 x 1粒重
これら収量構成要素を1つずつ丁寧に調査・分析することで、目標収量に届かなかったのは、栽培のどの時期に問題があったのかを調べることができます。お米の収量構成要素は、品種の持ち味を十分に引き出す栽培ができたかどうかをチェックできる大切な要素なのです。学生たちは、今後の実験実習を通して、作物生産方法の理解をさらに深めていく学びを進めていきます。最後には、精米したお米を炊飯し、食べ比べをして、実験実習の学びを噛み締める予定です。


植物性食材生産実験実習II
食産業学群食資源開発学類の3年生を対象とした後期開講科目です。前期開講科目「植物性食材生産実験実習Ⅰ」に引き続き、主な作物、蔬菜類などの園芸作物や花卉について、一般に行われている秋から冬にかけての生産管理法、水稲の収量解析方法、その他、農作物の生産現場に応用されている知見や技術について学びます。 (全15回)
指導教員プロフィール

左から、中村教授、鳥羽講師
・中村 聡(なかむら さとし):食産業学群 教授
家畜の飼料や甘味料のシロップ原料のほか、バイオマスエネルギー資源として期待されているマルチな作物「スイートソルガム」について、その能力を最大限に発揮できる栽培法の確立を目指して毎日研究しています。
・鳥羽 大陽(とりば たいよう):食産業学群 講師
より良いイネの品種改良を目指し、日々イネを理解することに研鑽しています。作物の持つ生命力, そのポテンシャルを解明し, 人類のために生かすことを目指します。
<参考>
米どころ宮城の水稲生産を実践で学ぶ“田植え実習”を実施しました/植物性食材生産実験実習I /食資源開発学類
小学生を対象としたプログラム, ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~「お米博士になろう〜大学のお米研究最前線〜」を太白キャンパスで開催しました/食産業学群 鳥羽研究室・赤澤研究室
野菜の栽培を通して学ぶ食材生産の現場/食材生産・加工実習Ⅰ/食産業学群