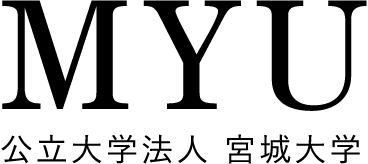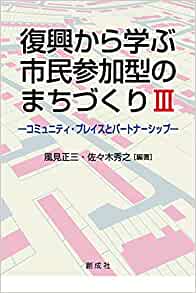新着情報
22.11.02
「とみやどにおける持続可能なまちづくり」「震災復興から学ぶ市民参加のまちづくりの3部作」が日本環境共生学会賞2冠/風見研究室・佐々木研究室
事業構想学群風見研究室・佐々木研究室が、これまで取り組んできた「とみやどにおける持続可能なまちづくり」「震災復興から学ぶ市民参加のまちづくりの3部作」の業績により、日本環境共生学会で2022年度学会賞(環境活動賞)・学会賞(著述賞)の2冠を達成しましたのでご案内いたします。
古来と未来、人々がクロスする交流ステーション「とみやど」
「とみやど」は、かつての宿場町の面影が残る『しんまち地区』で、地域の歴史的な資源や背景を活かした観光交流の拠点と、起業・創業の実践・チャレンジをサポートする拠点です。宿場町の歴史・文化など富谷市の魅力の一端を伝えるとともに、地域の稼ぐ力を創出し、地域経済の活性化を推進します。共創ラボのロゴマークには「やわらかい発想で柔軟にアイデアを出す拠点づくり」への想いが込められており、富谷市の市章と宮城大学のMをモチーフに、多様なイノベーションの創造をイメージしつくられました。
佐々木研究室・風見研究室 富谷市との連携プロジェクト 富谷宿観光交流ステーション「とみやど」内に「宮城大学×富谷市・共創ラボ」オープン




「プロジェクトには宮城大学が参画し、バックキャストによる事業目標を設定し、事業を進めていることから、学術的な知見も蓄積している。こうした持続可能な体制、仕組みによるエリアリノベーション事業は、他地域における持続可能なコミュニティ創成並びに地域活性化に応用可能な多くのシーズを提供している点においても、環境共生社会の進展、地方創生に寄与すると考えられるため、環境活動賞に相応しい。」として評価を受けました。
研究情報
|
「復興から学ぶ市民参加型のまちづくり」の全 3 部作
風見 正三(事業構想学群教授)/佐々木 秀之(事業構想学群准教授)の著作であり、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の復旧・復興まちづくりの過程で、被災地において実践されてきた数多くの挑戦的な取り組みとそのプロセスを、実践者自身の手で専門家でない一般の読者にも分かりやすくまとめたものです。第 1 部(2018)は中間支援組織の観点でまとめられたものであり、第 2 部(2020)は宮城県内の 7 つのソーシャル・コミュニティビジネスの事例を紹介したものです。また、第 3 部(2021)は宮城県内のコミュニティ・プレイスの事例や行政と民間の共同事業の事例を紹介しています。
復興から学ぶ 市民参加型のまちづくり -中間支援とネットワーキング-
本書は、東日本大震災に遭遇し、多大なる苦難を超えて再生を遂げつつある被災地の復興まちづくりの系譜をたどり、「震災復興」というプロセスから何を学ぶことができるのかについて、復興過程において重要な役割を持ってきた「市民参加」「協働」「中間支援」という視点から考察を進め、今後の復興まちづくりへの指針を提示するものである。
復興から学ぶ市民参加型のまちづくりⅡ―ソーシャルビジネスと地域コミュニティ―
震災復興過程で立ちあがった7つのソーシャルビジネスモデルが、いかにして地域再生に貢献したのか検証した。
復興から学ぶ市民参加型のまちづくりⅢ
-コミュニティ・プレイスとパートナーシップ-
東日本大震災からの復興過程における地域コミュニティ主体の取り組みを検証した『復興から学ぶ市民参加型のまちづくり』シリーズの最終巻。本巻では、宮城県内における8つの地域コミュニティの拠点の検討をもとに、コミュニティ・プレイスのあり方についての考察を試みている。
「これらの知見は、SDGs をはじめとする持続可能な地域開発を考える上で、非常に有益なものであり、著作というかたちで広く共有できることは、環境共生の進歩及び発展に大きく貢献するものである。」として高い評価を受けました。
研究情報
|
日本環境共生学会賞2冠を受けて、風見教授は「この度、東北の復興と未来を展望する2つの業績について、日本環境共生学会賞を頂きましたこと、本プロジェクトに携わって参りました多くの関係者を代表し、感謝を申し上げます。「震災復興から学ぶ市民参加のまちづくりの3部作」は、東北復興の教訓を現場の視点から編纂したものであり、これからのリジリエントな社会の実現に寄与するものと期待しております。また、「とみやど」は、地域の財産である宿場町を再生し、新たな交流人口を創出する持続可能なまちづくりの拠点であり、この地に創設された富谷市と宮城大学の「共創ラボ」は、地域主体の様々なプロジェクトを生み出していく地域未来共創の拠点となることが期待されます。」とコメントしました。
また、佐々木准教授は「実際に地域に入ると予想も出来ないことの連続でしたが、この過程での経験が今では得難い経験となっています。「とみやど」や復興プロジェクトには、多くの学生も関わってきました、今後も地域の魅力を最大限に引き出せるような、共創プロジェクトを生み出していきたいと思います。」と意気込みます。
今後も宮城大学の共創プロジェクトにご注目ください。
日本環境共生学会とは
人間生活を取り巻く自然環境・居住環境の共生に関する研究を行うとともに、これらの分野に携わる研究者、市民、行政担当者、実務者等による研究成果の発表と相互交流により、人類の営みと環境との調和・共生を対象とする固有の学問体系の確立を目指す学会です。「環境活動賞」は広く環境共生活動に顕著なる貢献をなした個人または団体を表彰、「著述賞」は優れた学術的貢献をなした会員を表彰するものです。
教員プロフィール

・風見 正三 (事業構想学群 教授)
東北から日本の未来を発信するための持続可能な地域づくりの研究や実践を進めています。地域の真の豊かさを追求していくコミュニティビジネスの視点から持続可能な地域産業やライフスタイルの在り方を考察し、コモンズ社会の創造に取り組んでいます。21世紀は、地域の人々が主体となり、個人も地域も共に豊かになるシナリオを実現する時代です。こうした目標に向けて、コモンズの視点やコミュニティビジネスの手法から様々な地域で持続可能な地域創造プロジェクトを提案・実践し、地域主体のまちづくりによるサステイナブルコミュニティの実現を目指していきます。
・佐々木 秀之 (事業構想学群 准教授)
地域の資源・歴史を活かしたまちづくり・地域ビジネス・地域コミュニティの創造に、理論と実践の両面から取り組んでいます。東日本大震災後は「ソーシャルビジネスによる社会起業家の育成」「まちづくり協議会における復興地区まちづくり計画の策定支援」「ウェブサイトを活用したデジタルアーカイブシステムの開発」「復興地元学事業」等を実施しています。
<参考>
- 「とみやどにおける持続可能なまちづくり」「震災復興から学ぶ市民参加のまちづくりの3部作」が日本環境共生学会賞2冠/風見研究室・佐々木研究室
- まちづくりにおける合意形成の不備をなくすファシリテーションシステムの実証実験
- 宮城大学×GM7×FUJISAKI「宮城のジェラートセット」がリリース
- 宮城大学地域創生学類の学生が取り組む 「センキョ割 in 多賀城市」プロジェクト
- 「みやぎ蔵王ハーモニー花回廊」計画、日本ガーデンツーリズム[周遊部門]へ登録が決定
- 佐々木研究室の学生がキャンパスベンチャーグランプリ東北で奨励賞を受賞
- CP実践論を学ぶ学生たちが七ヶ浜町の現地フィールドワークを実施しました
- 「ICT を活用した効果的・実践的な探究学習コンテンツの 構築に関する実証研究」
- 「地域資源と地域資金の循環による持続可能な協働まちづくり」共同研究開始
- 佐々木研究室・風見研究室 富谷市との連携プロジェクト 富谷宿観光交流ステーション「とみやど」内に「宮城大学×富谷市・共創ラボ」オープン
- 「塩竈の藻塩を使ったジェラート」メニューを共同開発、塩釜水産物仲卸市場で販売演習
- 地域創生学類で学ぶ学生が、復興庁主催「復興ビジネスコンテスト2020」で2部門受賞
- 利府町「tsumiki」がグッドデザイン賞を受賞/風見研究室・佐々木研究室
- 「森の学校」プロジェクトが2020年度日本環境共生学会学会賞2部門受賞
- 風見正三研究室が「森の学校」基本構想で第26回日本不動産学会長賞を受賞
- 風見研究室・佐々木研究室による「富谷しんまち活性化プロジェクト」宮城大学×富谷市
- 2/7 七ヶ宿町総合計画ワークショップを開催しました
- 3年ぶりに復活する「Rifu-Co-Laboみんなの未来づくりワークショップ」
- 9/7-8 Reborn-Art Festivalとの協創プロジェクトを石巻市荻浜で実施しました