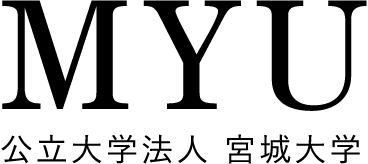Keyword
ウシ、繁殖管理、受胎率向上、OPU、人工授精
新たなウシの生産技術を構築する
研究内容・実践活動
現在、ウシの繁殖に用いられている人工授精は、100年以上も前に開発された技術で、その基本的な方法は今も変わっていません。近年、人工授精の受胎率は様々な要因により低下し、胚移植(ET)と変わらないレベルにまで来ており、現在の高能力牛に用いる繁殖技術としては限界に来ているといえます。これまでウシでは人工授精以外にも、受精卵移植、体外受精(IVF)、生体卵胞卵子吸引・体外胚生産(OPU-IVP)などが実用化されています。しかし、精子に比べ卵子の数が少ないことがネックとなり、産仔数に占めるET産仔の割合は10%(大呂、2019)に留まっています。我々は、卵胞発育の過程で退行したり休眠したりしていたこれまで利用されていなかった卵胞に注目し、これらの卵胞を活性化して胞状卵胞に発育させる技術(卵胞活性化)を開発しOPU-IVPにより胚生産の増加を目指しています。現在活性化の可能な卵胞は二次卵胞以降の卵胞ですが、将来的には卵胞数の多い一次卵胞についても活性化法の開発も行っていきます。従来の繁殖技術と我々が開発した卵胞活性化を融合することで採卵数を飛躍的に増やし、肉用牛の新たな生産技術を構築していきたいと考えています。
産学官連携の可能性
卵胞活性化には、卵巣内の胞状卵胞数を増やすこと以外にも卵巣の状態を改善する働きがあると考えています。このため、受胎率の低下したウシに卵胞活性化を行うことで受胎率が向上する可能性も期待できます。これらの点については、今後とも研究を積み重ねる必要がありますが、ウシ飼養する農家、特に肉用牛の繁殖にとっては、有用な技術になることが予想されます。
牛群の繁殖管理を委託されている獣医師、多頭飼育を行っている牧場、受精卵を短期間に増やしたいあるいはウシの育種改良を迅速に行いたい牧場の皆様との連携を希望致します。次世代に向けた新たな肉用牛の生産技術をいっしょに構築していきましょう。